「原発に関わる人々も、技術者も、市民も、すべての人々が〈安全〉について強く求めていくと同時に、守るべき根本的なものは何なのかを確認しなければなりません」
scroll
- Profile後藤 政志さん
- 元原子力プラント設計技術者。原子力市民委員会委員。1989年より東芝で原子炉格納容器の設計に従事する。退職した二年後に東京電力福島第一原発事故が発生。以降、技術者として事故の状況解説や問題点を指摘し、原発の安全性や再稼働の矛盾などについて訴えている。
「原子力プラントに携わった技術者として、最低限の節操として、自分の知っていることをすべて話す義務がある。今、私にできることは、原発の技術的な問題点・危険性について、きちんとお話しする。決して原子力に反対だ・賛成だということを言うつもりはなく、原発とはこういうものです、と説明します。そこから先はそれぞれが考えていただきたいと思います」
東電福島第一原発事故翌年の2012年の講演の冒頭で、後藤政志さんはそう述べた。
後藤さんは、1989年から原子炉の設計技術者として原発をつくる場に携わっていたが、現役時代から原発を扱う側の安全性への考え方に異議を唱えていた。2009年の退職から二年後、実際に福島で発生してしまった過酷事故に衝撃を受け、もっと早くにもっと大きな声で警鐘を鳴らすべきだったと後悔が募った。以降、講演やインターネット等を通して、原発の仕組みや日本の規制基準の問題点について積極的に情報発信を行っている。

消えた反省と非現実的な道筋
国内の原発で過酷事故が起き、広範囲に甚大な被害が及んだにもかかわらず、10年経った現在、日本政府は事故などなかったかのように原発再稼働もよしとするエネルギー政策に転じている。事故後、政府や国会による事故調査委員会などが設けられたが、事故の原因究明は一年足らずしか行われず、いまだ未解明のことが多く残るままだ。また「どんなに発生確率が低くても、過酷事故に至る可能性のあることは無視せず、徹底的に安全策をとるべき」という原発事故の教訓と反省はどこかへ消え、山積するさまざまな事故後の問題に対しても現状からかけ離れた策が多いと、後藤さんは指摘する。
「リスクは〈被害の大きさ〉と〈発生確率〉で表現されますが、気をつけて見ないと、膨大な被害があり得るのに、確率が低ければいいと考えられがちです。しかし起きる確率が低くてもその被害が小さいわけではなく、発生時には取り返しのつかないリスクを持つものもある。いまだ原発のリスク評価は発生確率だけを見ています」

欧州では、通常の廃炉は 50〜70年くらいかけて行われる。放射線量が高い段階では手を付けずに時間を置いてから解体するなどしていくのが一般的な廃炉工程だという。そうすれば廃炉に関わる作業員の被ばくも少なくて済む。燃料デブリ* についても、格納容器からの取り出しが安全に行えるかどうかにも疑問符が付くが、回収したものをどこでどう処理するのか、あるいはどのように保管・管理するのかについても、研究段階で詳細がまったく定まっていない。1〜3号機に残る燃料デブリは一基あたり約 200〜300トン超で、凄まじく高い放射線を放出しており、被ばくや新たな事故の可能性も出てくるため、取り出しを急ぐべきでないというのが、後藤さんの見解だ。
「東京電力は廃炉計画について、今後 30〜40年あれば可能という見積もりを出していますが、極めて非現実的です。事故を起こしていない普通の状態の原発の廃炉作業にも、最も短くて 30年かかる。でも福島第一はあれだけ厳しい事故が起きた状態の炉なので、100〜200年の単位の話になる。先に可能であると言ってしまったため、できる見通しもないのに、計画に向けて少なくとも努力をしていると見せかけているのでしょうね。汚染水なんかも同じです」

最も大切なものは何か
廃炉や汚染土・汚染水の処理を含む諸問題について、また再稼働が検討される中で、事故を教訓として位置づける技術者の不在。しかし、原子力に詳しい技術者に安全について任せればいいというわけではない。安全が最も重要であると考える技術者と、そうではない技術者と、はっきりと分かれるものだという。
「何が最も大切なのか。その基本をまずしっかりと決めてから、その方針に適任な技術者をあてないと、よからぬ方向へ行きます。人の価値観は千差万別なので、考えによって無闇に選別されるべきではありませんが、少なくとも『人体に有害な放射性物質は絶対に環境中に出さずに管理する』というような大前提に沿うことのできない技術者は論外です」
最も大切なもの。それは経済性・利便性か、それとも人の命や、不安なく毎日のささやかな暮らしが続くことか・・・10年前に、それらは私たち市民にも突きつけられた問いではなかったか。
原発の安全神話は、原子力を扱う側だけが作ったものではなく、それにのみ込まれていった市民の側に非がないわけではない。「戦争と同じ」と後藤さんは言う。
「トップが悪かったからだ、それに従っただけだ、では済まされる話ではありません。いつの間にか世の中の空気や価値観がズレていき、先の戦争に突入していった。原発も構造としては同じですよね。安全神話はそうしてできていった。原発に関わる人々も、技術者も、市民も、すべての人々が〈安全〉について強く求めていくと同時に、守るべき根本的なものは何なのかを確認しなければなりません」
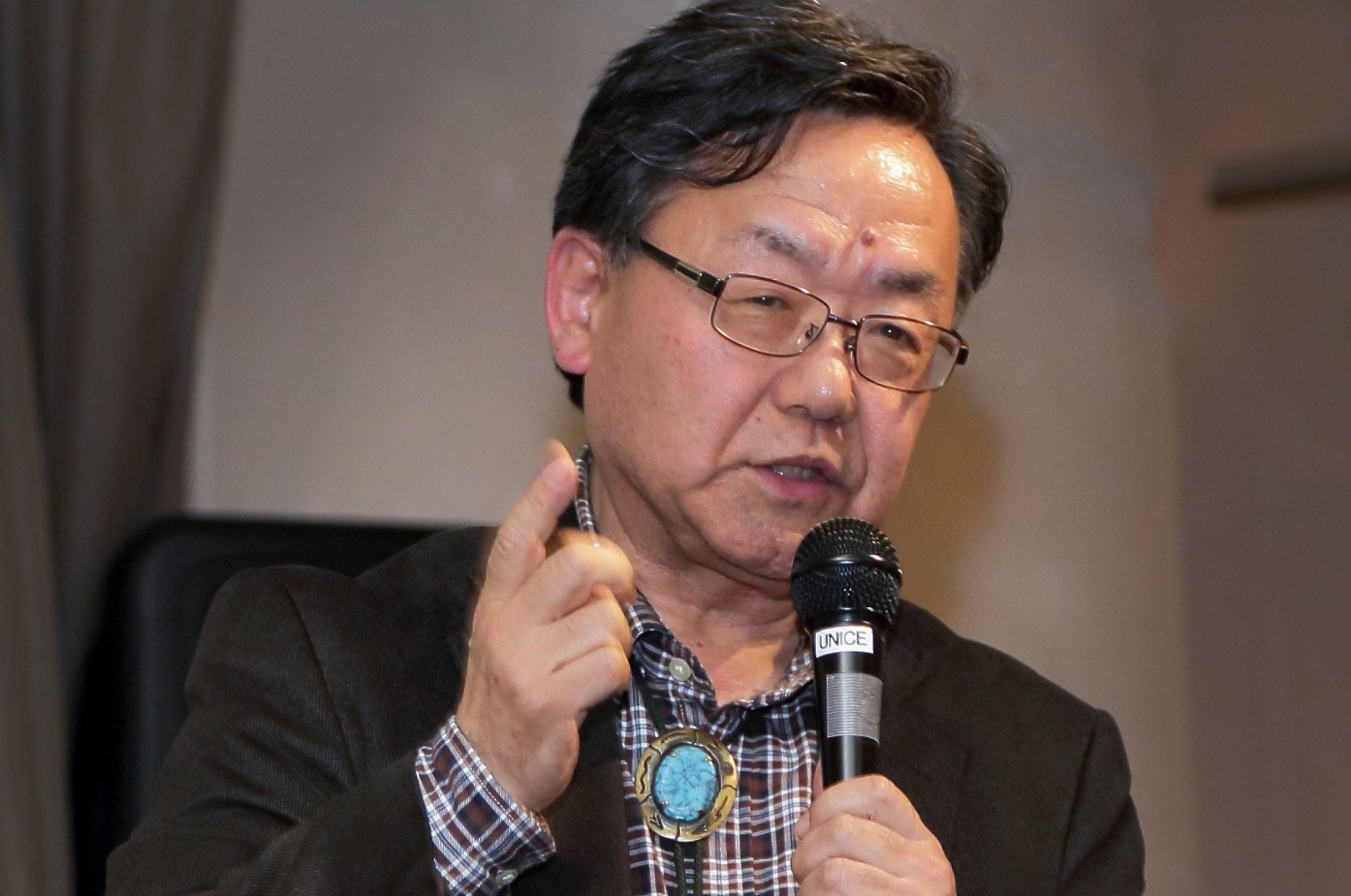
安全な暮らしを求める権利
原発に絶対安全を求める市民に対し、これまで原子力を推進する側は「世の中に絶対安全はない。車は?飛行機は安全ですか?」といった相対的な安全論にすり替えてきた。こうした議論の中で、技術的な「安全とは何か」が揺らいでいった。東電福島第一原発の事故が起きてから、電力会社をはじめ規制当局は原発の安全性が「絶対とはいえない」と認めたが、市民が安全性の確保を訴えると、いまだに「絶対安全を求めるのは非科学的」という反論をする。しかし、そうした姿勢は、解決できない技術課題や原発の持つ本質的な安全性、つまり危険性に対して、向き合わないことを意味していると、後藤さんは強調する。
「科学的な意味で、世の中に〈絶対〉というものはないと私も思っています。しかし、原発の万が一の被害というのは修復不可能な深刻なものなので、原子力においては、絶対的な安全が保証されない限りは使用してはならない。修復できないようなリスクがない状態を〈安全〉というのです。技術を提供する人間は、技術に影響を受ける立場の人々に対して、そのデメリットの大きさについて説明責任がある。リスクの判断をしてもらうための説明が、いまだ原子力では果たされていない。被害を受ける可能性のある市民にとって、絶対安全を求めるのは当然のことです」

「安全とは、というのは立場によって変わるものですが、個人として、市民は安全を求める権利を持っている。人権の問題です。一人ひとりがその権利を持っているという根本が揺らいだら、すべてが揺らぐ。私は技術者のはしくれとして技術のことを語っていますが、科学技術と人間の権利、すべてはつながっている。根底に人権への意識を置いていない技術というのはダメな技術だと思いますね」
自分たちの持つ権利を認識し、自分たちの安全に関わる情報をやり過ごさずに考えていく姿勢が市民にもなければ、暮らしを守っていくことはできない。私たちが使う電気の、さまざまな発電方法に伴うリスクを知ることは、難解な科学技術の話ではない。「もしも」の想像ではなく、実際に、取り返しのつかない原発事故が発生した後の世界に私たちは生きている。
- *燃料デブリ:事故により、原子炉圧力容器内の炉心燃料が原子炉格納容器の中の構造物(炉心を支える材料や制御棒、底部のコンクリートなど)と一緒に溶けて固まったもの


